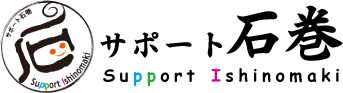サポート石巻とは
2011年3月の震災直後、国内外からの支援をきっかけに、被災者である代表が立ち上げた無償のボランティアグループです。法人格を持たず小さな規模で、たくさんの協力者と共に活動を続けています。
【活動内容と信念】
発災直後の生活支援・現地調整から始まり、自立支援、防災意識の啓発など、多岐にわたる活動を展開しています。
何よりも大切にしているのは「公平な支援」。目立つ地域だけでなく、見えにくい困難にも手を差し伸べ、支援の格差を埋めることを目指しています。
【震災を通じ感じたこと】
被災地では、支援者との考え方や文化の違いが混乱を生む場面が多く、中間役の必要性を痛感しました。支援の偏りや「被災者」の定義に対する温度差にも直面しましたが、私たちは「震災前と生活が変わったすべての人」を被災者と捉えています。
石巻では「助け合い」の心が薄れたようにも感じましたが、震災当初の経験を思い出すたび、その大切さを再認識します。今も心が癒えない市民は多く、表向きの笑顔の裏に苦しみがあることも少なくありません。
【未来への想い】
現在は、石巻以外で防災・減災の講演やアドバイスを行っています。私たちの経験を「繰り返さない」ために、自分事として考えてもらうことを大切にしています。被災地に行けなくても、できる支援はたくさんあります。
活動の継続は、多くの無償支援者の支えあってこそ。金華さばのデザインやWebサイト制作なども含め、たくさんののご協力に心から感謝しています。
「支援する側」「される側」ではなく、同じように不安を抱え、傷を抱え、それでも誰かのために動こうとする人たち(被災者)と共に活動しています。
特別な知識や経験がなくても「誰かの役に立ちたい」「自分にできることをしたい」という気持ちがあればもうあなたは仲間です😃
時間が十分になくても、遠くにいても、できる支援はたくさんあります。
被災者が手がけたキンカサバグッズを手に取ることも、大切な応援のひとつです。
あなたのペースで、あなたらしい形で。
その一歩が、きっと誰かの心に届きます
あなたの一歩が、きっと誰かの心の灯になります。
一緒に、静かに、そして確かに、歩いていきませんか
これからもどうぞよろしくお願いいたします